指導の準備
指導案の立て方、教材の作り方について説明いたします。
良い指導に良い準備は欠かせません。
内容をよくお読みになってから、チェックテスト2を記入し送信してください。
1.指導案の立て方
指導案の立て方
子供がわくわくできる指導案を立てるにはどうすればいいでしょうか?
それには、子供をよく観察しアイディアをたくさん出すことです!そのようなときに役立つのが、マインドマップです。
【マインドマップとは?】
頭の中のアイディアを、それぞれの脳のやり方で紙上で目に見えるようにする思考ツールです。
真ん中に「テーマ」を書き、そこを起点に「ブランチ」と呼ばれる枝を四方へ伸ばして、関連するワードをつなげていきます。【利用するメリットは?】
①短時間で頭の中にある情報をたくさん書き出すことができる
②1つの情報からアイディアを大きく広げることができる
③広げたアイディアの中から、簡単に必要情報を取り出すことができる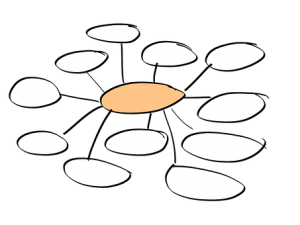
2.目標の考え方
目標の考え方
マインドマップを使って指導の目標を考えてみましょう!
指導の目標には、大きな目標の【今月の目標】と、それを達成するための週ごとの小さな目標【週ごとの目標】があります。
目標の設定には、以下【1】~【4】の流れがあります。
【1】当月までの保護者対話で来月の勉強の進め方について確認をとる。
保護者の要望と子供の様子を考えてベストプランを提案しましょう!【会話例】
保護者: 「足し算はだいぶできるようになってきましたね。最近『おおきなかぶ』の絵本が気に入ってるんですよ。」スタッフ: 「では、来月の国語は『おおきなかぶ』を使って指導を進めるのはどうでしょうか?また算数は足し算の繰り上がりに挑戦したいと思います!」
保護者: 「いいですね。」
【2】来月の目標を具体的するためにマインドマップで書き出してみる。
例)
・ステップアップしたい内容は?
・復習が必要な内容は?【3】内容を絞ってさらにマインドマップを広げる。
例)
・ゲーム感覚で進めるのは?
・工作などおりまぜるのは?
・子どもが今興味あることと関連させるのは?【4】今月の目標と週ごとの目標を立てる。
※70%の達成率が可能な目標を立てます。
難しすぎても簡単すぎてもNGです。子供たち自身がやる気をもって挑戦するためには、指導内容を考える側がスモールステップを意識して子どもの乗り越えるのに最適な目標を立てることが大切です。【今月の目標】
1ヶ月の指導で何が出来るようになるのか大きな目標を設定します。
例)
国語:「おおきなかぶ」のストーリーの並び替えができる
算数:2けた+1けたの足し算の繰り上がりができる【週ごとの目標】
今月の目標を起承転結(4週)に分け、
1回分の指導の目標を設定します。例)
第1週目~起~
国語:「おおきなかぶ」の第1場面の穴埋め問題ができる
算数:1けた+1けたの足し算の繰り上がりを思い出すことができる
第2週目~承~
国語:「おおきなかぶ」の第2場面の穴埋め問題ができる
算数:2けた+1けたの足し算の繰り上がりの練習を始める
第3週目~転~
国語:「おおきなかぶ」の第3場面の穴埋め問題ができる
算数: 2けた+1けたの足し算の繰り上がりの苦手ポイントを練習する
第4週目~結~
国語:「おおきなかぶ」の第1~3場面の穴埋めテストができる
算数: 2けた+1けたの足し算の繰り上がりの確認テストができる3.予定の考え方
予定の考え方
マインドマップを使って予定を考えてみましょう!
まず【週ごとの目標】から1回分の指導の予定を決めます。事前に指導のイメージができているかいないかで指導の良しあしが決まってきます。【ガッツの指導の基本の流れ】
挨拶
↓
目標・予定・約束の確認
↓
先週の復習
↓
今日の挑戦
↓
ふりかえり
↓
挨拶【予定の作成方法】
【1】週ごとの目標から組み立てられた1回分の指導の流れを、マインドマップで書き出す。
※教材のアイディアも書き入れるとGOOD
【2】マインドマップに書きだした予定をまとめる
※挨拶やふりかえりの部分も記入する4.ふりかえりをしましょう
ふりかえりをしましょう
指導後には毎回ふりかえりをしましょう!
ふりかえりの目的は、その日の指導について把握し次回の指導につなげることです。
指導が終わった直後にふりかえるのがポイントです。
出てきた答えに「来週はどうするのか?」の問いかけを自分自身にしましょう。
以下のチェック項目を参考に毎回指導後にふりかえりをしましょう。【良かったこと】
□笑顔だったことはありましたか? その理由はなんですか?(ex.学習内容・声かけ・教材)
□予定通りに進んだこと はありましたか?
□予想以上に出来た ことはありましたか?
□今回クリアしたことはありましたか?
□問題が改善したことはありましたか?
□新しい発見はありましたか? (ex.好きなもの・喜ぶ・やる気になる言葉や動作・得意なこと)【問題点】
□嫌だ・やらないといったことはありましたか?その原因はなんですか? (ex.学習内容・声かけ・教材)
□予定通りに進まなかったことはありましたか?
□予想以上にできなかったことはありましたか?
□問題が続いていることはありますか?
□スタッフから注意したことはありましたか?その理由は何ですか?(ex.態度・言葉・学習内容)
□もっと工夫できたことはありましたか?【保護者対話】
□評価を受けたことはありましたか?
□改善をお願いされたことはありましたか?
□希望があったことはありましたか?
□質問があったことはありましたか? (ex.事務局への質問、指導への質問)
□次回の指導日を確認しましたか?
□交通費はいただきましたか?【事務局】
□指導報告書の期限や入出報告の期限は守れましたか?
□教材についてアドバイスもらいたいことはありますか?
□指導目標・計画についてアドバイスもらいたいことはありますか?
□指導の進め方についてアドバイスもらいたいことはありますか?
□保護者から質問はあった場合事務局へ報告しましたか?5.報告書の書き方
報告書は、保護者も読むので、見てわかりやすいまとめ方をします。
報告書は、ふりかえりをもとにを書いていきます。【評価基準】 ☆☆☆☆☆ 一人で満点 ☆☆☆☆ 一人でよくできた ☆☆☆ 一人で合格 ☆☆ サポートありでできた ☆ サポートありでむずかしかった 以下は、報告書の各項目で書くことです。
(※〇:必須項目 ✕:任意提出)
項目 提出 内容 今月の目標 〇 ・当月の達成したい目標を書きます。週ごとや、項目ごとにできるだけ詳しく書きましょう。
ex)算数:繰り上がりの足し算に挑戦する
国語:文章をゆっくり丁寧に読む週ごとの目標 〇 ・各週で具体的に教えたこと、それについての生徒の反応を書きます。指導の感想ではありません。
・指導の結果・様子は、良かったこと→できなかったところの順で書きます。GOOD 漢字のよみは100点。書きは70点で~の部分が苦手。
→ただよくできたではなく、数字を入れることでより伝わります。BAD 漢字のよみは100点だったが、書きは70点だった。
→できたことと、できなかったことを同時に伝えてしまうことで、できたことが打ち消されてしまいます。ポイント ※できたことはできた、できなかったことはできなかったと、分けて考えることが大切です。
保護者対話でもこのような説明の仕方に注意しましょう。備考 ※一週間に複数回指導がある場合は、1つの枠内に日付で分けて入力してください。
例)7月5日と8日に指導がある場合
→7月5日
・・・・・
7月8日
・・・・・
と冒頭に記入
※5週目に指導がある場合→4週目にまとめて記入します。記入の仕方は上記と同様です。
※月に5回指導があるにも関わらず、報告書には4回分の記入しかない場合も違反となります。
※複数のスタッフが一人の生徒を担当している場合、日付の横に名前を記入しましょう。
例)
7月5日(山本)
・・・・・
と冒頭に記入各週の下にある空欄 〇 ・指導の評価をします。プルダウンで選択できます。(☆で5段階) 得点 ― ・保存更新ボタンを押すと、各週の☆の数が反映され得点欄に得点が表示されます。 応援メッセージ 〇 ・生徒と保護者に、来月へ向けてのメッセージを書きます。
それにプラスして「楽しく取り組めた」などの感想も書くことができます。写真(右下の空間) × ・指導中や指導後に生徒と撮った写真を載せます。
1カ月に1枚でOKです。掲載方法 携帯のカメラで撮影⇒以下のアドレスに所定の形式で送信
アドレス:report@soulc.com
件名:せいとめい201106
本文:未入力ポイント 【1】件名の生徒名は、フルネームをひらがなで入力。
【2】年月日は送信月を半角で入力。ひと桁の月は06など、0を付記する。
例)7月報告書分の写真なら、201107
11月報告書分の写真なら、201111
【3】一度送信した後に、再度別のメールを送った場合は上書きされる。
【4】本文は未入力でOKです。

